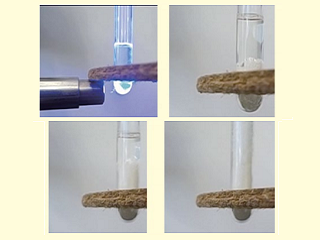【総説】有機トランジスタの評価法
本記事は、東京大学大学院新領域創成科学研究科物質系専攻 工学部応用化学科 岡本 敏宏准教授に執筆いただいたものです。
これまでの精力的な研究により、有機半導体材料の性能指標であるキャリア移動度(以下、移動度と略す)は、現在実用的に用いられているアモルファスシリコンを超え、10 cm2/Vs以上の移動度が報告されるまでになっている1-3)。この移動度の向上により、実デバイスにおける重要な基本素子である有機電界効果トランジスタ(Organic Field-Effect Transistor, OFET)を用いたディス...