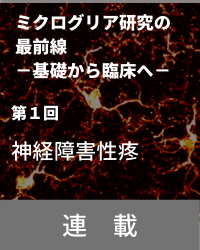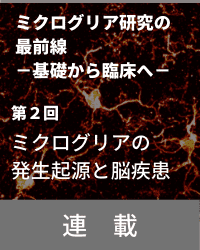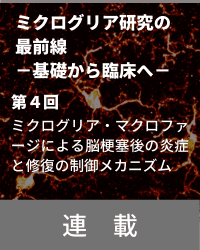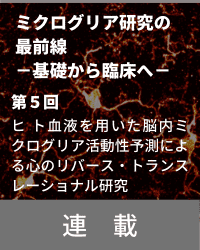【連載】ミクログリア研究の最前線−基礎から臨床へ− 「第3回 脳内貪食細胞の謎に迫る」
本記事は、和光純薬時報 Vol.89 No.1(2021年1月号)において、東京大学 大学院薬学系研究科 薬品作用学教室 河野 玲奈様、池谷 裕二様、小山 隆太様に執筆いただいたものです。
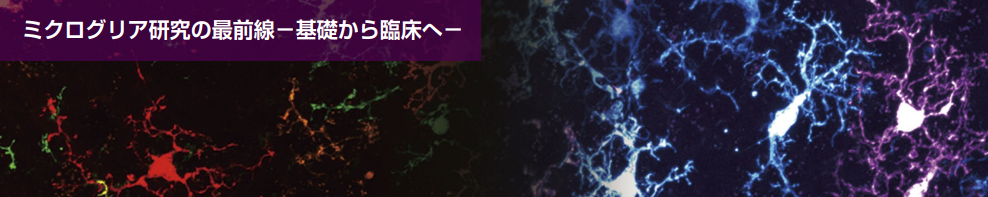
はじめに
貪食は免疫機構における重要なプロセスである。体外から侵入してきたウイルスや病原菌だけでなく、体内で産生される細胞の死骸や異常な凝集たんぱく質など、あらゆる不要物を対象として、貪食の" プロフェッショナル "である食細胞がその役割を担う。
脳内では、組織常在性マクロファージ(この呼称には批判的な見解もあることに留意されたい)とも呼ばれることもあるマイクログリアが主要な免疫細胞且つ食細胞と考えられており、その貪食能に関して多くの研究がなされてきた。しかし近年、マイクログリアだけでなくアストロサイトも貪食能を有することが示された1)。
アストロサイトはグリア細胞の一種であり、神経伝達物質の取り込みや神経細胞への栄養因子などの供給、血液脳関門の形成など非常に多彩な機能を持つ。その多彩な機能と並行して行われる貪食は、マイクログリアによる貪食とは様々な点において異なる特性を有する。そこで本稿ではアストロサイトとマイクログリアによる貪食の特色や役割の違いを比較しながら、脳内における貪食について考察する。
アポトーシス細胞の貪食
Damisahらは、1つのアポトーシス細胞に対する貪食を、アストロサイトとマイクログリアの間で比較している2)。著者らは、蛍光色素とレーザー照射による1細胞レベルでのアポトーシス誘導技術を用いて 1 つの神経細胞に細胞死を誘導し、周辺のグリア細胞の応答を2 光子イメージングによってin vivo で観察した。その結果、マイクログリアは細胞体と細胞体近位の樹状突起を、アストロサイトはより遠位にある微細な突起を貪食していた。この結果について著者らは、アポトーシス細胞が提示する"eat me" シグナルが、細胞体周辺と遠位の突起との間で異なる可能性を提唱している。
また、薬理学的なマイクログリアの除去を行ったマウス脳では、アストロサイトが代わりに細胞体を貪食・除去したことも報告している。ただし、マイクログリアによる除去はアポトーシス誘導より約20時間後に生じ、アストロサイトによる除去は50時間後以降に生じるという時間的な差異があった。
Löövらは培養細胞を用いてアストロサイトとマクロファージとの貪食を比較した 3, 4)。初代培養脾臓マクロファージまたはアストロサイトに、pH 感受性色素(酸性条件下で蛍光を発する)でラベルされた神経細胞片を添加して貪食の様子を観察したところ、マクロファージでは 5 時間後には酸性小胞内に取り込まれたことを示す蛍光が確認され、3日後には死細胞の凝集した核が消失していたことから、分解が確認された。それに対し、アストロサイトでは 12日後にようやく死細胞核の消失が確認された。なお、その間常に酸性条件を示す蛍光はほとんど確認されなかった。
この観察結果から、アストロサイトはマクロファージに比べ、貪食物の分解に時間を要すること、またリソソーム内の pH が高いことが示唆された。著者らはこの高い pH のために貪食物の分解に時間がかかると考え、これを検証するためリソソームの酸性化を引き起こす微粒子をアストロサイトに処置した。その結果、5日後の時点で分解が促進されていることが確認された。マクロファージと比較してアストロサイトのリソソームの pH が高く保たれるメカニズムは不明であるものの、これが原因となって貪食物の分解に時間的差異が生じた可能性がある。
マイクログリアとアストロサイトは、互いが正常に機能している際に役割を分担するだけではない。小西らが最近発表した興味深い報告によれば、マイクログリアに遺伝学的手法を用いて細胞死を誘導すると、アストロサイトがマイクログリアの死骸を約4日間のうちに貪食、除去する5)。また、マイクログリアの貪食機能を低下させると、アストロサイトが代わりに神経細胞などの死細胞片を貪食する。つまり、マイクログリアの貪食機能が不全となった際にはアストロサイトがその機能を補償する役割を担うと考えられる。
病態時の貪食
病態時のアストロサイトとマイクログリアによる貪食の違いについては、森澤らにより行われた中大脳動脈閉塞(MCAO)による脳虚血モデルを用いた研究において直接的な比較がなされている6)。マイクログリアは虚血コア領域およびペナンブラ領域(血流量は低下しているが細胞死は免れている領域)に存在し、大小様々なサイズの細胞片を貪食するのに対し、アストロサイトはペナンブラ領域において比較的小さいサイズ(10μm2 以下)の細胞片を貪食していた。
さらに、貪食マーカーであるGalectin-3(貪食機能に関与するレクチン)やリソソームマーカーの発現を比較すると、マイクログリアでは MCAO から3日後にピークを迎え 14日後にはコントロールレベルに戻るのに対し、アストロサイトは 7日後にピークに達し、14日後でも発現の亢進が持続していることが示されている。またその分子メカニズムとして、虚血時にアストロサイト特異的に発現が上昇しているATP-binding cassette transporter A1 (ABCA1、脂質トランスポーター)に着目しており、ABCA1 のノックアウトによりアストロサイトの貪食が抑制されることを示している。なお、マイクログリアでの ABCA1 の上昇は見られないことから、マイクログリアでは異なる伝達経路が働いていることが予想される。
シナプスの貪食
発達期において、視神経からの投射を受ける外側膝状体(dLGN)では過剰なシナプスがシナプス刈り込みを受ける。このシナプス刈り込みに、マイクログリアとアストロサイトの双方が関わることが2つのグループから報告されている7, 8)。どちら の細胞についても関連する受容体が報告されており、アストロサイトは Mer tyrosine kinase (MERTK)とMultiple EGF-likedomains 10 (MEGF10)、マイクログリアでは補体経路であるC3-CR3 シグナル、という互いに異なる経路を介したシナプス貪食機構が報告された。
しかし、両者とも神経活動依存的に貪食が制御される点は共通している。また、マイクログリアに関しては C3-CR3 シグナル以外にも、CD47-Signal Regulatory Protein α (SIRPα)シグナルが "don't eat me"シグナルとして働くこと、Sushi repeat protein X-linked 2 (SRPX2)という内因性タンパク質が VGLUT2 陽性のシナプス特異的に貪食を抑えることなどが報告されている9, 10)。
これらの知見より、マイクログリアによるシナプス貪食においては多彩なシグナル経路を介することで除去されるべきシナプスを緻密に区別していると考えられるが、アストロサイトに関しては詳細な検証が進んでいないのが現状である。
貪食における役割分担の考察
平常時および病態時において、マイクログリアと比較してアストロサイトは、比較的小さいサイズの細胞片を貪食する傾向がある2,6)。また、その取り込みと分解にはマイクログリアに比べ長時間を要することが、リソソームの pH と関連づけて示唆されている3, 4)。そして、アストロサイトは神経細胞など他の脳内細胞と同じく外胚葉由来であるのに対し、マイクログリアは中胚葉由来とされており、その由来に伴って基本的な細胞の性質が異なる点も、アストロサイトとマイクログリアの違いを考える上で重要な点であろう。
アストロサイトは脳の物理的な構造の維持に重要な支持細胞であり、一定のテリトリーを持ってお互いに離れて存在している11)。また、神経細胞の機能を補助する様々な役割を持つことを考えても、アストロサイトは大幅な構造変化を生じることのない範囲で貪食を行うのが合理的であるだろう。
一方でマイクログリアは、分枝した突起を絶え間なく動かし続ける、非常に動的な細胞である。また、脳内における細胞死やウイルス感染などを素早く感知するための受容体を多く発現し、高い遊走性を有する。そして貪食の際には突起を退縮させアメボイド状の形態に変化することができるため、大きな構造物の貪食に適している。このように細胞本来の機能や形態からも、本稿で紹介した貪食の役割分担はそれぞれの細胞の特徴を活かしていると言えるかもしれない。
一方で、マイクログリア非存在下やマイクログリアの貪食機能が不全となった状況においては、アストロサイトが通常であれば貪食しないサイズおよび量の死細胞片を貪食する。アストロサイトの貪食能亢進のメカニズムは明らかではないが、正常時はマイクログリアがアストロサイトの貪食を抑制している可能性が示唆されている2, 5)。いずれにせよ、アストロサイトがマイクログリアの貪食機能を補償しうることは、生物にとって重要であると考えられる。
また、時間スケールの差異に関しては、マイクログリアが限界量を貪食した際に、補償的にアストロサイトの貪食機能が上昇する仮説が提唱されている12)。しかしながら、Damisahらの実験により、マイクログリア非存在下でも、アストロサイトは細胞体のような大きいサイズの貪食を行うことが(時間を要するものの)可能であることが示されている。これらの知見を合わせて考えると、アストロサイトによる貪食物の緩慢な分解は、貪食を誘起する分子メカニズムの違いに起因している(マイクログリアに依存した機構ではない)と考えられるが、この差に生物学的な利点があるのかは明らかではない。
Löövらは、アストロサイトが抗原提示を行うためにリソソームの pHを高く保ち、抗原の分解を抑制するという仮説を主張している3)。しかし、アストロサイトが抗原提示機能を実際にもつことはこれまでに報告されておらず、マイクログリアが抗原提示を行う可能性を含め、今後の検証課題である。アストロサイトとマイクログリアの貪食における役割分担を詳細に解明するには、受容体活性化、取り込み、リソソーム形成、分解といった貪食の各プロセスの分子メカニズムを、両細胞種で明らかにし、直接的に比較することが必要である。
シナプス貪食に関しては、興奮性や抑制性といった性質をはじめとするシナプスごとの特徴によって、アストロサイトまたはマイクログリアのどちらに貪食されるかが決まる可能性がある。先述したように、近年、マイクログリアに関しては複数の因子を介してシナプス貪食が緻密に制御されていることが示されている。そのような背景もあり、現時点ではマイクログリアが主要なシナプス貪食の担い手であると考えられ、アストロサイトにおいても、より詳細なシナプス貪食制御の検証が求められている。そのためには、アストロサイトとマイクログリアによるシナプス貪食を同時にイメージングする系の確立が必要である。
終わりに
マイクログリアとアストロサイトによる貪食の役割分担という観点で知見を比較してきたが、2 種類の細胞を同時に同条件で比較した知見は依然として少ない。本稿で紹介したシナプスやアポトーシス細胞に加え、アミロイドβやミエリンなどもアストロサイト、マイクログリア双方による貪食が報告されている13-16)。これらの貪食対象に関しても、細胞種特異的な遺伝子操作を行いアストロサイトとマイクログリアによる貪食を同時に比較し、詳細な分子メカニズムを解明することで、アストロサイトとマイクログリア間の役割分担が明らかになるであろう。
参考文献
- Cahoy, J. D. et al. : J. Neurosci., 28 (1), 264 (2008). DOI: 10.1523/JNEUROSCI.4178-07.2008
- Damisah, E. C. et al. : Sci. Adv., 6 (26), eaba3239 (2020). DOI: 10.1126/sciadv.aba3239
- Lööv, C. et al. : Glia, 63 (11), 1997 (2015). DOI: 10.1002/glia.22873
- Lööv, C. et al. : PLoS One., 7 (3), e33090 (2012). DOI: 10.1371/journal.pone.0033090
- Konishi, H. et al. : EMBO J., e104464 (2020). DOI: 10.15252/embj.2020104464
- Morizawa, Y. M. et al. : Nat. Commun., 8 (1), 28 (2017). DOI: 10.1038/s41467-017-00037-1
- Schafer, D. P. et al. : Neuron, 74 (4), 691 (2012). DOI: 10.1016/j.neuron.2012.03.026
- Chung, W. S. et al. : Nature, 504 (7480), 394 (2013). DOI: 10.1038/nature12776
- Lehrman, E. K. et al. : Neuron, 100 (1), 120 (2018). DOI: 10.1016/j.neuron.2018.09.017
- Cong, Q. et al. : Nat. Neurosci., 23 (9), 1067 (2020). DOI: 10.1038/s41593-020-0672-0
- Halassa, M. M. et al. : J. Neurosci., 27 (24), 6473 (2007). DOI: 10.1523/JNEUROSCI.1419-07.2007
- Magnus, T. et al. : J. Neuropathol. Exp. Neurol., 61 (9), 760 (2002). DOI: 10.1093/jnen/61.9.760
- Wyss-Coray, T. et al. : Nat. Med., 9 (4), 453 (2003). DOI: 10.1038/nm838
- Mills, E. A. et al. : Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 112 (33), 10509 (2015). DOI: 10.1073/pnas.1506486112
- Heckmann, B. L. et al. : Cell, 178 (3), 536 (2019). DOI: 10.1016/j.cell.2019.05.056
- Hughes, A. N. et al. : Nat. Neurosci., 23 (9), 1055 (2020). DOI: 10.1038/s41593-020-0654-2