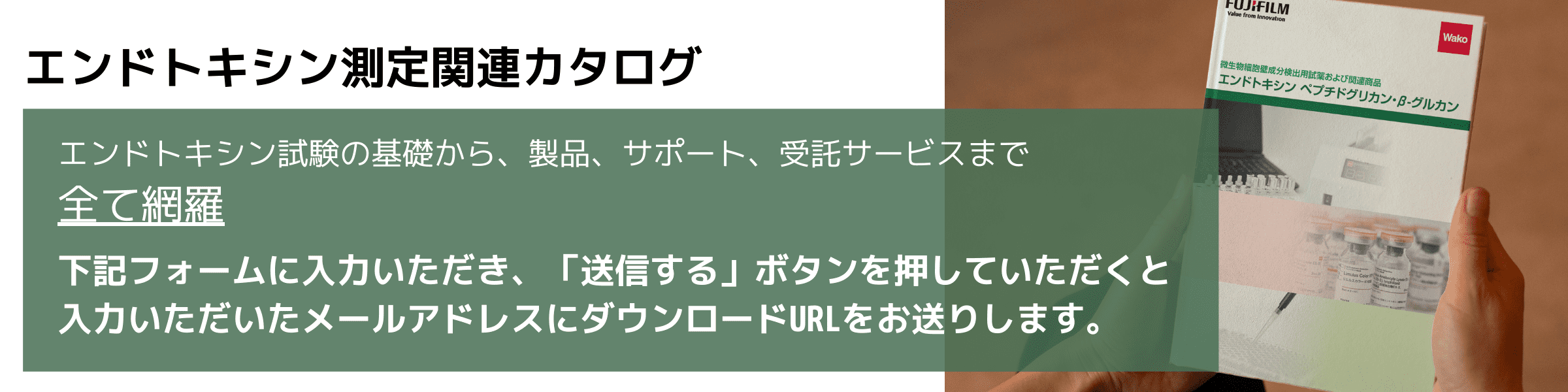【連載】Talking of LAL「第23話 添加回収試験で知りたいこと」
本記事は、和光純薬時報 Vol.64 No.2(1996年4月号)において、和光純薬工業 土谷 正和が執筆したものです。
第23話 添加回収試験で知りたいこと
前回、添加回収試験における 2 つの疑問点についてお話ししました。すなわち、ET 添加回収試験において(1)試料からの影響を分類し区別する必要はないか、(2)どのような ET を使用するべきかの 2 つです。今回は、添加回収試験で何を知りたいかについて考えてみたいと思います。
これらの疑問の原点として、「どの状態のエンドトキシンを測定するべきか」という問題があります。すでに紹介したように、エンドトキシンは、そのミセルの大きさが一定でないため、絶対的な生物活性を持っていません。そして、このことが測定における影響を複雑にしていると思われます。
すなわち、エンドトキシンが試料に添加されることによりその活性が可逆的に変化した場合、変化の前と後のどちらの活性を測定するべきかを十分考える必要があるのです。
この問題に関して、二つの考え方があると思われます。その一つは、「リムルス試験の結果はその時点の生物活性を反映していると考えられるから、測定値をそのまま採用する。」という考え方です。
また、第二の考え方は、「変化後の活性は変化前の活性に戻る可能性があるから、変化前の活性を測定するべきである。従って、添加回収試験におけるエンドトキシンの回収率を測定値にかけて、潜在的なエンドトキシン活性を推定する方法がよい。」というものです。
第一の考え方は、試料が他の環境に移された場合、試料中のエンドトキシン活性がどのように変化するかについて全く考慮していません。例えば、試料が医薬品の場合、試料が体内に投与されたときに試料中のエンドトキシン活性が体液との接触によって高くなる可能性などを考慮していないということです。
以前にご紹介した金属イオンによるエンドトキシン活性の低下に関する実験では、リムルス試験とウサギの発熱性は同じように変化しましたから、変化を受けたエンドトキシン活性をそのまま測定するという考え方も妥当であるように思えます。しかし、エンドトキシン活性自体がさらに変化する可能性が否定されたわけではないことにも留意する必要があります。
また、第二の考え方では、測定しようとする試料中のエンドトキシンの活性変化が一定の割合で起こり、その変化が添加回収試験に使用するエンドトキシンと同じ程度であるということを前提としています。一般的には、試料に混入するエンドトキシンの性質を予測することが困難であるため、第二の考え方で推定したエンドトキシン活性が、本当に試料に混入する前の活性を表しているかどうか疑問があります。
どちらの考え方にも、それぞれ一理あるように思われます。しかし、現時点でどちらかの方法が良いということはできません。これまで、エンドトキシンの添加回収試験において、エンドトキシン自身の活性変化についてはあまり考慮されていなかったように思われます。今後、測定目的を考慮した上で、測定したエンドトキシンの意味を考えてみる必要があると思われます。
さて、ここで今回のテーマの添加回収試験で知りたいことについて考えてみたいと思います。添加回収試験は、リムルス試験の有効性を確認するために行う試験の一つです。今回考えてきたエンドトキシン活性の変化も、リムルス試験でエンドトキシンの活性を測定する上で非常に重要な問題です。
しかし、その変化が十分に解明されていない現在、この問題をリムルス試験自体の有効性評価に組み込むのは適当でないと思われます。従って、現在のところ、添加回収試験で確かめるのは、エンドトキシン活性が変化しにくい条件で検討を行う「試料が反応に与える影響」に絞るべきではないでしょうか。
関連記事