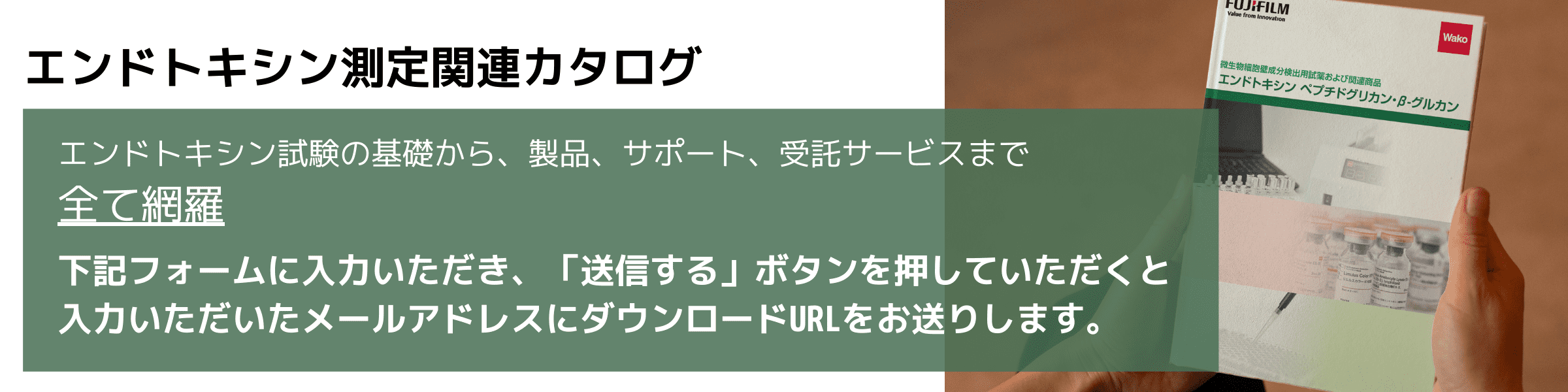【連載】Talking of LAL「第25話 ペプチドグリカン」
本記事は、和光純薬時報 Vol.64 No.4(1996年10月号)において、和光純薬工業 土谷 正和が執筆したものです。
第25話 ペプチドグリカン
今回は、エンドトキシンと同様、細菌の細胞壁成分であるペプチドグリカンについてお話ししたいと思います。ペプチドグリカンは、その生物活性こそエンドトキシンに比べて低いのですが、エンドトキシンと共存するとエンドトキシン活性を増強したりすることが知られています。
グラム陰性菌はエンドトキシンとペプチドグリカンの両方を持っていますから、自然界ではこの二つの物質の共存がよく起こると思われます。ペプチドグリカンは、リムルス試薬には反応しませんが、カイコ体液由来の SLP 試薬で検出することができます。
ペプチドグリカンは、N-アセチルまたは N-グリコリルムラミン酸と D-アミノ酸を含むことを特徴とする糖ペプチドのポリマーで、細菌の細胞壁成分として菌の形状の保持に重要な働きをしています。エンドトキシンがグラム陰性菌のみに存在するのに対して、ペプチドグリカンはグラム陽性菌とグラム陰性菌の両方に存在し、グラム陽性菌では細胞壁の最外殻に分厚い層を、グラム陰性菌では外膜の内側に薄い層を形成しています。
エンドトキシンもペプチドグリカンも持っていない古細菌(メタン細菌、高度好酸性好熱菌等)を除くと、ほとんどの原核生物がペプチドグリカンをその細胞壁に持っています。すなわち、細菌が存在するところにはペプチドグリカンが存在すると考えられます。
ペプチドグリカンの化学構造は、各細菌によって異なるものの、いくつかの種類に分類されています。詳細は参考文献1, 2)を見ていただくとして、大まかな構造の一例を挙げると次の通りです。
すなわち、β-1,4 結合した N-アセチルグルコサミンと N-アセチルムラミン酸の繰り返し構造を持つ糖鎖に、ムラミン酸のカルボキシル基を介して、3 ないし 4 個のアミノ酸からなるペプチドサブユニットが結合し、このペプチドユニットが直接または他のペプチドに架橋されることにより網目様の構造をとり、全体としては袋状になっています。
ペプチドグリカンは、化学的に比較的安定であり、酸にもアルカリにも溶けません。従って、精製を行う場合も、酸処理や加熱処理など、かなり過激な条件で行われています3)。もちろん、ペプチドグリカンを分解し可溶化するリゾチームのような酵素が広く生物界に存在していますから、自然界でペプチドグリカンのみがどんどん蓄積していくということではありません。リゾチーム等の酵素でペプチドグリカンを処理して分子量を小さくしていくと、水溶性の分解物もできてきます。
ペプチドグリカンは種々の生物活性を持っています4)。その例を挙げると、in vitro では、マクロファージ、B リンパ球、T リンパ球等の免疫応答細胞に対する種々の作用、血小板の破壊、繊維芽細胞の増殖促進、骨吸収の促進、補体の活性化等が、in vivo では、体液性免疫応答の増強または抑制、細胞性免疫の増強、細網内皮系の刺激、一過性の白血球減少ならびにその後の白血球増加、インターフェロン誘導因子の作用を高める作用、自然抵抗力の強化、実験自己免疫疾患の誘導、発熱作用、エンドトキシンの毒性に対する感受性を高める作用、睡眠の促進ないし抑制、類上皮肉芽腫形成、結核菌等で処理した部位に出血壊死性炎を惹起する作用、急性ならびに慢性の毒性等があります。
これらの活性の多くはエンドトキシンの作用と共通していますが、その活性の強さは、エンドトキシンに比べると弱いようです。
エンドトキシンは、もちろん、最も強力な発熱性物質であり、これを管理することは非常に重要です。しかし、微生物由来の生理活性物質はエンドトキシンだけではなく、ペプチドグリカンやβ-グルカンをはじめ種々の物質が自然界に混在していることも、我々は考えるべきではないでしょうか。
参考文献
- 松橋通生:化学総説, 6, 113-134 (1974).
- Labischinski, H. and Maidhof. H. : "In Bacterial Cell Wall", Elsevier, Amsterdam, p.23-38 (1994).
- 駒形和男編:「微生物の化学分類法」, p.14-26(学会出版センター)(1982).
- 小谷尚三、高田春比古:薬学雑誌, 103, 1-27 (1983).
関連記事