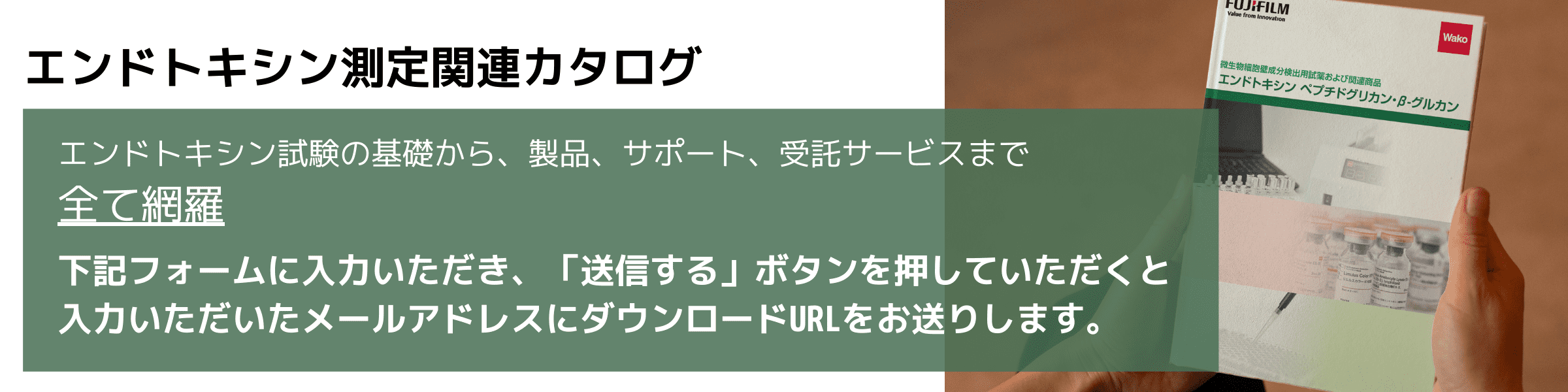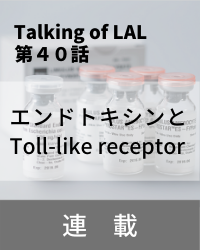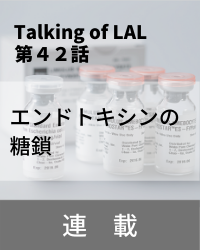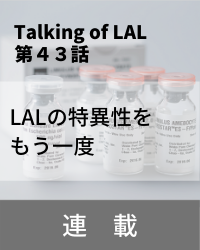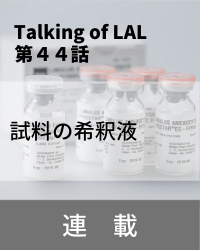【連載】Talking of LAL「第41話 エンドトキシンショック」
本記事は、和光純薬時報 Vol.68 No.4(2000年10月号)において、和光純薬工業 土谷 正和が執筆したものです。
第41話 エンドトキシンショック
今回は、エンドトキシンの生体に対する影響の中から、エンドトキシンショック、特にそのメディエーターについて考えてみましょう。
ショックとは、種々の原因によって循環系の均衡破綻によって急性循環不全が生じ、諸臓器・組織の機能不全をきたす病態とされています1)。ショックは、循環血液量減少性、心原性、敗血症性、神経原性、アナフラキシーなどに分類されており、その特徴は血圧の低下です。エンドトキシンに最も関連したショックは、敗血症性ショックです。
エンドトキシンの生物活性の中で、発熱性、致死活性と共に、ショックはその代表といえるでしょう。大量のエンドトキシンを動物の血管内に投与すると、ショックが起こります。この場合、ショックはエンドトキシン刺激による生体反応の結果であり、その過程では種々のメディエーターが関与していると考えられています2)。
1960 年代のカテコールアミン、ヒスタミン、セロトニン、キニンに始まり、プロスタグランジン、トロンボキサン、ロイコトリエン、血小板活性化因子、NO、サイトカインと様々な物質が主役として登場してきました。1990 年代の主役は、やはり TNF、IL-6 等の炎症性サイトカインと思われます。
さて、臨床の方面では、ショックを治療する目的で、これらの主役を働かせないようにする方法が試みられてきました。例えば、エンドトキシンに対するモノクロナール抗体や TNF 抗体、IL-1 抗体などです。
しかし、これらの治療法は、モデル系では効果が認められましたが、実際の臨床検討では有用性が十分証明されず、医薬品として認可されるには至っていません3,4)。エンドトキシンショックにおいて、エンドトキシン自身や各種サイトカインは、最も重要な因子でないということなのでしょうか。
最近、エンドトキシンショックのメディエーターの主役候補として注目されている物質に、内因性カンナビノイドがあります5)。カンナビノイドとは、大麻の麻薬成分で、脳内で多量に発現している CB1 レセプターを介して、多幸感、幻覚記憶の障害など、多彩な精神神経反応を引き起こす物質です。
CB1 の他、脾臓、マクロファージ等に発現している CB2 も、カンナビノイドレセプターです。CB1、CB2 に対する内在性のリガンドとして発見された物質が 2-アラキドノイルグリセロール及びアナンダマイドで、これらを内因性カンナビノイドと呼んでいます。
内因性カンナビノイドは、アラキドン酸の誘導体で、麻薬作用の他、血圧低下作用、アポトーシス誘導などの作用が報告されており、LPS の作用で単球や血小板から放出されると考えられています6)。すなわち、LPS 刺激で内因性カンナビノイドという血圧を低下させる物質が放出されるわけです。
さらに、これらの内因性カンナビノイドがポリミキシン B に結合することが発見されました7)。ポリミキシン B はエンドトキシンと強く結合することが知られる抗生物質で、これを固定化したカラムは、血中エンドトキシンの除去を目的とした医療用具として使用されています。
このカラムはエンドトキシンショックの治療に用いられますが、エンドトキシンのみならず内因性のカンナビノイドを除去することにより治療効果があるという可能性が示されたわけです。このあたりの研究は、鹿児島大学の丸山征郎教授の研究室で行われており、今後興味深い論文が発表されることが期待されます。
これまで、エンドトキシンショックのメディエーターとして非常に多くの物質が注目されてきました。しかし、エンドトキシン抗体や各種サイトカインの拮抗剤が治療薬として認知されなかったことを考えても、最も重要なメディエーターが何かは明らかになっていないと思われます。
内因性カンナビノイドは、今後どのように研究されていくかは予想がつきませんが、現在最も注目されている物質の一つであることはまちがいありません。今後の研究の進展が期待されます。
参考文献
- 小川道雄 :「知っておきたい侵襲キーワード」, p. 32-35,(メジカルセンス)(1999).
- 中野昌康 , 小玉正智(編):「エンドトキシン」, p. 60-61,(講談社サイエンティフィク)(1995).
- 中野昌康 , 小玉正智(編):「エンドトキシン」, p. 203-226,(講談社サイエンティフィク)(1995).
- 真弓俊彦 他 : Lisa, 6, 860(1999).
- Varga, K. et al.: FASEB, 12, 1036(1998).
- Wagner, J. A. et al.: J. Mol. Med., 76, 824(1998).
- Wang, Y. et al.: FEBS Let., 470, 151(2000).
関連記事